美しい車とは、美しく”つくられている”車のこと。
世界的なカーデザイナー、ジョルジェット・ジウジャーロの言葉には、デザインと生産が切り離せないものであるという哲学が込められています。

先日幕張メッセで大規模に開催されたクラシックカーの祭典「オートモービルカウンシル」の今年のテーマは、生ける伝説のカーデザイナーGiorgetto Giugiaro展「世界を変えたマエストロ」。
本会にはなんとジウジャーロ氏が来日。
会期中2日間にわたりトークショーが開催され、彼の長年のキャリアのなかで育まれた思想、そして日本の製造業との関係について語りました。
そこに浮かび上がったのは、「思想を守るには”どうつくるか”を知らなければならない」という、デザインに携わるすべての人に響くメッセージでした。
ジウジャーロと日本―デザイン思想を育てた”出会い”
ジウジャーロ氏は芸術家の家系に生まれ、父も祖父も画家という環境で育ちました。幼少期から色や形に強い関心を持ち、もともとはファインアートの道を志していましたが、子どもの頃から特別に自動車に興味があったわけではなかったと語っています。
イタリアの北西部、トリノから南に100kmほど行った小さなコムーネ・ガレッシオに生まれたジウジャーロ氏は、中学卒業後トリノに出て、日中はファインアートの学校に通い、夜はフィアット社が運営する工業学校でテクニカルな知識を学びました。
高校在学中、先生の勧めで初めて自動車のスケッチに挑戦し、そこから自動車デザインの道に進むことになります。当時フィアットでは、まだ「デザインセンター」という概念が生まれつつある黎明期。アートのバックグラウンドを持つ彼にとって、工業製品としての車作りはカルチャーショックだったと振り返ります。しかし、その経験の中で、美術で学んだ構成や造形の考え方が活かせることに気づき、創造力と技術を融合させた独自のスタイルを築いていきました。
ジウジャーロ氏のキャリアはフィアットから始まり、イタリアの名門カロッツェリア「ギア」や「ベルトーネ」へ進みました。そのなかで、1960年代初頭のいすゞとのプロジェクトをきっかけに日本を訪れた経験が、彼にとって一つの大きな転機となります。
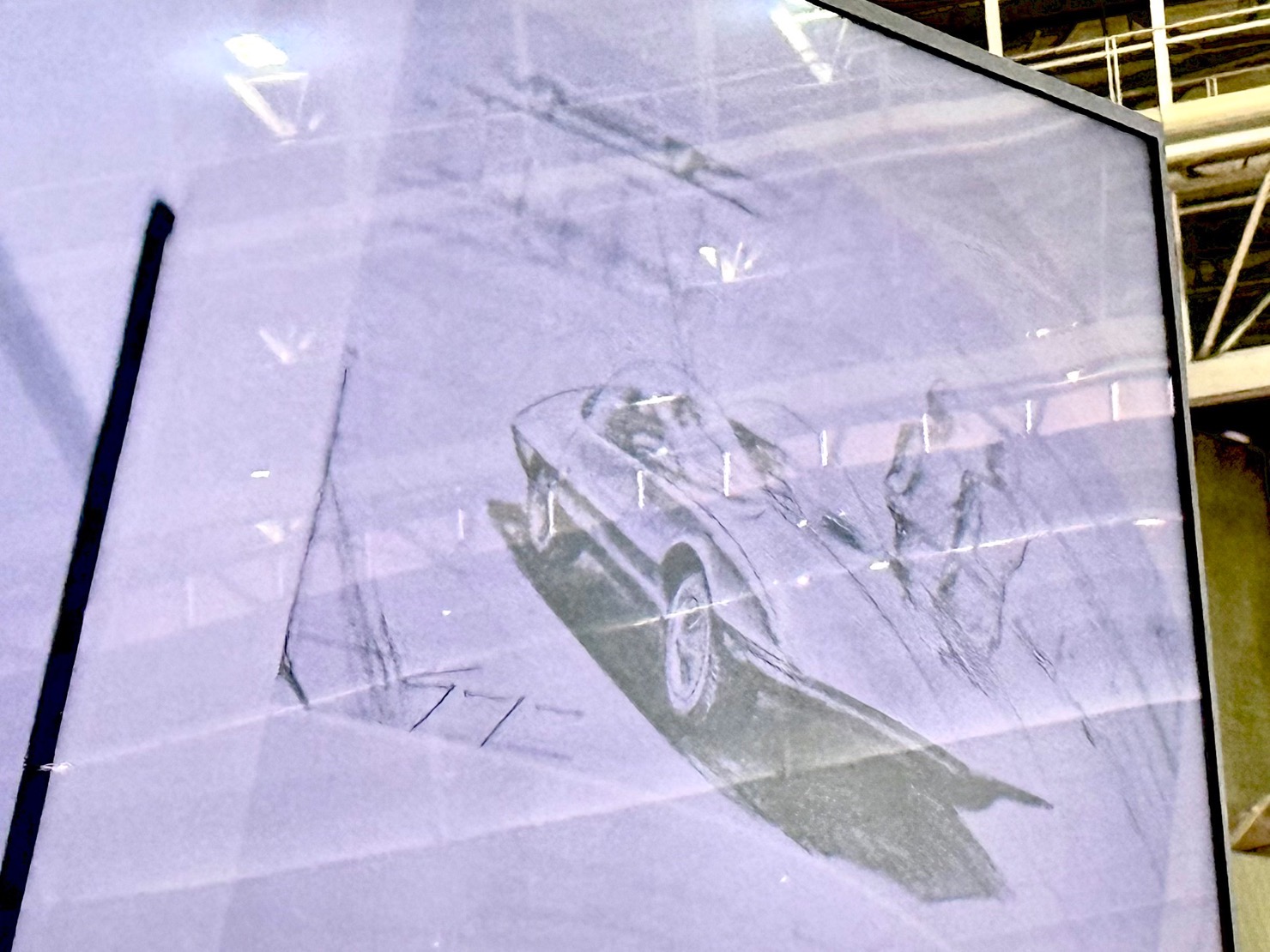
彼は1970年に開催されたモーターショー向けに、いすゞ117クーペのショーモデルを手がけました。そのエレガントで現代的なフォルムは大きな反響を呼び、量産化の強い要望が生まれました。結果として、117クーペは少量生産ながらも市販化され、世界初の「量産されたイタリアンデザインの日本車」として語り継がれています。
しかし、デザインから量産への移行には大きな困難が伴いました。工業的な制約や生産設備の未熟さの中で、「夢をどうやって”つくれるもの”に落とし込むか」という課題に直面したのです。この経験は、ジウジャーロ氏にとって重要な転機となりました。
彼は「117クーペの量産化を通じて、デザインとは量産設計を踏まえたうえで成り立つべきものであると痛感した」と語り、それが後のイタルデザイン設立の思想的な礎となったと明かしました。イタルデザインは、単なるスタイリングだけでなく、生産現場に実装可能な設計提案までを行えるスタジオとして他のカロッツェリアと一線を画す存在となったのです。
「イタリア以上に温かく、敬意にあふれた歓迎だった」と彼は語り、日本を「第二の故郷」と呼ぶほどの感銘を受けました。またこの体験が、彼に独立の決意を与えます。1968年、彼は自身のデザイン会社「イタルデザイン(ITALDESIGN)」を設立。アルファロメオ・アルファスッド、フォルクスワーゲン・ゴルフなど、数多くの名車を世に送り出し、イタルは1100人を超える大規模組織へと成長していきます。
のちにイタルデザインはフォルクスワーゲングループに売却され、ジウジャーロ氏は退任。現在は、息子ファブリツィオ氏と共に設立した「GFG Style(Giorgetto & Fabrizio Giugiaro)」に拠点を移し、活動を続けています。
GFGは、規模を絞った独立系スタジオとして、自動車だけでなくモビリティや建築、ブランドデザインにまで領域を広げています。トークショーでは詳細に触れられませんでしたが、量産現場と連携しながら、柔軟なアプローチでデザインを実現しているといいます。
日本のものづくりとの共鳴
「日本は、この製品の品質を引き上げるために、驚くべき推進力を発揮してきました」。そう語るジウジャーロ氏にとって、日本の製造現場は価値観を共有できる協業相手であり続けています。
いすゞ、東洋工業(現マツダ)、ダイハツ―1960年代から続く日本企業との協業を通じて、彼は日本の”ものづくり”に深い敬意を抱くようになりました。
機能性を追求しながら、美しさを犠牲にしない。それは彼の「構造とスタイルは一体であるべき」という思想と、見事に響き合うものでした。
プロトタイプは夢想ではない―量産との対話でこそ、思想が磨かれる
「プロトタイプとは、習慣を超えるための試みであり、同時に経済的なエンジニアリング手段でもある」。ジウジャーロ氏は、デザインが形だけでは成立しないことを繰り返し強調しました。量産車は、規格、コスト、安全性といった現実的な条件の中で設計されます。その制約の中にこそ、デザイナーの思想が試される余地があります。単なるアイデアではなく、「かたちにして届ける」こと。それが、プロダクトデザインの真価であるという信念です。
特に印象的だったのは、日本の軽自動車市場における彼の経験でした。「最も難しい車にこそ、スタイルが求められる」。限られたスペース、コスト、規制。それらをすべてクリアしながら、美しさを保つには、生産工程への深い理解が不可欠なのです。
“正当性”のあるデザインとは何か?
では、ジウジャーロ氏が語る「正当なデザイン」とは、どのようなものなのでしょうか。彼の答えは明快です。
「製品がどう作られているかを理解し、語ることができるデザイン」こそ、真に正当なデザインであること。
見た目の美しさだけではなく、素材、構造、量産プロセス―あらゆる現実的な条件を受け入れ、それでもなお成り立つスタイルにこそ、説得力があるといいます。
ジウジャーロ氏はまた、「美しさとは数学でもある」と語っています。
車や建築に見られる美しさには、比例やバランスといった数値的な根拠が内在しており、それは人間の顔のわずかな差異が印象を大きく左右するのと似ています。同じ構成要素であっても、ミリ単位の違いが個性を生み出す―その繊細さを意識することが、デザインにおいて大きな違いを生むと説いていました。
思想と量産は矛盾しない。むしろ、それは相互補完的な関係
このトークショーを通して、ジウジャーロ氏が伝えた最も大きなメッセージは、「思想と量産は対立するものではない」ということでした。むしろ、量産という現実と対話する中でこそ、思想は研ぎ澄まされ、説得力を得るのです。美しい製品は、美しい”つくり方”の上にしか成り立ちません。
彼の語る言葉、そして彼が手がけた数々のデザインが、その真実を静かに、そして確かに語っていました。筆者自身、ジウジャーロ氏の語る「エコノミカ(経済的)な視点」や「量産を前提にしたデザイン」という考えに強く共感しました。筆者がイタリアの製造業に関わっていた頃に、日常的に「夢だけではモノは作れない」と口酸っぱく言われ続けたことを思い出します。
また、ジウジャーロ氏がキャリアをスタートさせた戦後のイタリアは、第二次世界大戦での敗戦を経て、経済的にも厳しい状況に置かれていました。インフラも資源も乏しく、多くの産業が再出発を余儀なくされるなか、同国は粘り強く工業とデザインの融合を模索し、やがて世界に誇る製造業・デザイン大国としての地位を築き上げていきます。
その礎となったのは、まさにジウジャーロ氏のような一人ひとりの技術者・デザイナーの信念と革新性でした。限られた条件の中でも理想を追求し、思想と現実を巧みに融合させてきた先人たちの姿勢こそが、今日のイタリアンデザインの根幹を成していると言えるでしょう。
同時に、ジウジャーロ氏の思想の形成には、日本の製造現場との出会いが重要な役割を果たしていたことにも注目したいです。限られた制約の中でも美しさと機能性を両立させる日本のものづくりに対して氏は一貫して敬意を示しており、それが「構造とスタイルは不可分である」という哲学をさらに確固たるものにしていったように感じられます。
現在、日本の自動車メーカーをはじめとする製造業も、人材不足や海外の関税政策の影響など、様々な課題に直面していますが、厳しい状況に置かれた現場にこそ、光をあてていくことが求められているのではないでしょうか。“つくる”という営みが尊重される社会――それはジウジャーロ氏が高く評価した技術立国・日本の産業再生にもつながる道だと信じています。
